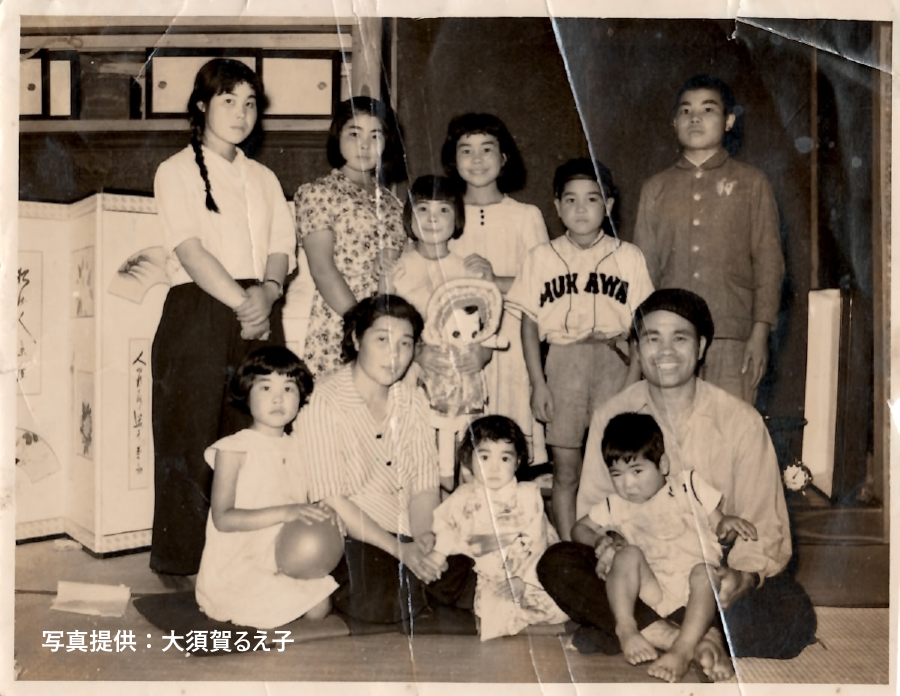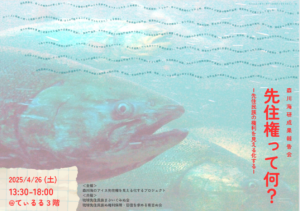すごい働き者のおばあさんだから、わたしが目覚めるともういない。畑にいるおばあさんを見つけて自分の親のように、とにかくおばあさんの後についてまわりました。薪(たきぎ)集めも一緒にやりましたよ。5歳の子どもだったけど、おとなと同じように柴を背負わせて歩かせるの。紐をきゅきゅっと縛ると緩みもしなくてしっかりしていました。休むときはそのまま仰向けになって柴の上に乗って休んだの。
この、おばあさんと一緒に柴刈りに行った話を母親にしたことがあるの。そしたら母親が、「こんなちっちゃい5歳の子どもにそんなことさせた」って怒ったの。びっくりしたよー。そういうおばあさんとの話を「言っちゃいけないんだな」っていう気持ちになって、それからあんまり言わなくなったの。
おじいさんとはよく一緒に魚を食べました。わたしが骨を出すと、このおじいさんがまん丸い目をして「食べろ!」って言うんです。5歳の子どもに、骨も食べろって言うわけ。わたしはびっくりしてじいさんをじっと見て、じいさんはわたしをずっと睨みつけるように見るわけ。わたしは、もぐもぐって何十回もその骨を噛んで、それこそ50回も100回もかじって飲み込んだっていう記憶があるの。
大きな船でアリューシャン列島まで行き、そこから小さな船に乗り換えてラッコの群れに近づく。毛皮を獲ったら、外貨を稼ぐために中国へ売った。おじいさんは単に雇われていたんだね。船員の服を与えられて働いていたのだけれど、肩に顕彰をつけて横浜の町を歩くと通りすがりの人に敬礼されたんだって。「田舎にいたらアイヌと言われて軽蔑されたけど、スッキリした」と言っていた。このおじいさんは、カムチャッカを通ってサンフランシスコまで行ったというんだからすごいよね。