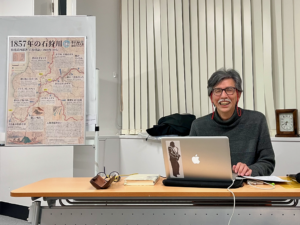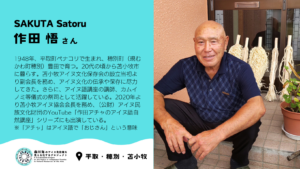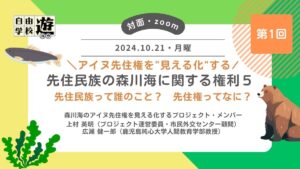井上 千晴(いのう えちはる)
浦河町生まれ。森川海のアイヌ先住権を見える化するプロジェクト副代表。 宇梶静江代表、一般社団法人アイヌ力(ぢから)事務局。
2024年12月1日(日)、立教大学にてドキュメンタリー映画「カムイチェプ」の上映会を行った。天気は晴れ。気温は16℃。当日の早朝、北海道から東京入りした私は20℃の気温差に体が驚いた。電車を乗り継ぎ立教大学に着くと、正門からの景色に再び驚いた。モリス館の風格と綺麗に色づいた大きなイチョウの木にとてつもなく感激した。
今回の映画上映会は、立教大学異文化コミュニケーション学部(石井正子教授)、森川海のアイヌ先住権を見える化するプロジェクト、特定非営利活動法人アジア太平洋資料センターの3団体主催で開催。会場とオンラインでの映画上映の他、本作品を撮った映画監督の藤野知明さんとハルコロの宇佐照代さんの対談も行われた。宇佐さんのトンコリとムックリの演奏を近くで聞くことが出来て幸せでした。イヤイライケレ。
映画「カムイチェプ」のカムイチェプとはアイヌ語で神の魚を意味し、鮭のことを表す。紋別アイヌ協会の畠山敏さんが長年、国や北海道に対し先住権の行使として鮭漁を求めてきましたが、話し合いが進展しないことから、2018年、許可申請をせずに鮭漁を試みましたが、警察が出動し、実行することができませんでした。その様子をリアルに映し世に出して下さったのが藤野監督である。
アイヌにルーツを持つ私だが、畠山さんとの面識はなかった為、交流があった母に上映会前日電話をした。「畠山さんってどんな人?」と聞いたところ、「良識がある人。その辺のアイヌとは違う。」と即答であった。

映画が始まると会場に足を運んで下さった100人近い方が、スクリーンに釘付けになった。衝撃的な場面がそのまま映し出されており、ぐっと唇を噛む自分がいたが、母が言っていた「良識がある人」が要所要所で伝わってくる。
映画を観終えた同世代の知人からは「畠山さんの生き様を見させていただきました。ここで私たちの世代が踏ん張らないといけないなぁ、と思って、勇気をいただきました。」と、上映会後すぐに感想を送ってくれた。本当にその通りである。畠山さんの頑張りを、先人たちが作ってくれた道を私たち世代がしっかりと受け止めて、繋いでいかなければならないと…。その意味をみんなで考えないと…。
この映画が、北海道の人にはもちろん日本中、世界中の方が観てくれたら、何かが変わる気がします。 上映会を終えて外に出ると、もう真っ暗。モリス館前のヒマラヤスギはクリスマスイルミネーションでキラキラしていた。携帯で写真を撮り北海道で待っている夫と息子に送信。打ち上げ会場のハルコロへ向かう。


参加者のアンケートより(一部抜粋)
道内に住んでるものとして畠山さんの行動記事のことはテレビや新聞で見聞きしていましたが、ご本人の想い、役所の対応等、自分もリアルにその場にいるかのように緊迫感を持って体感することが出来ました。時間をかけてドキュメンタリー映画にしていただいた藤野監督に心から感謝です。当然のアイヌの権利を奪っていた和人の一人として事実に打ちのめされそうですが、少しでも権利回復のために行動を起こしたいと思います。
禁止されている川で無許可で祭祀のためにサケを採って逮捕された件についてはニュースで見た時にはどうして許可を取らないんだろうと不思議に思っていましたが、今日映画を拝見できて、理由やお気持ちがとてもよくわかりました。アイヌの皆さんが納得できる形で解決することを願っています。そのためには行政、というよりまずはやはり多くの国民が問題を知り、合意が形成されることかなと思いますので映画はとてもいい手段だと思いました。
新聞報道やニュースで表面的な知識(のみ)はあったのですが、映像ではじめて、何がどのようにおこり、そしてどう動いていたのかがわかりました。今まで良く知らなかったことを恥じるとともに、紋別川で行われてきた、そしてアイヌの方々のもとのムラがあった場所を示される畠山エカシのことも知り、映像の力を改めて認識しました。
アイヌの先住権が奪われていることは知っていたが、今回の映画で具体的なことがしっかりと理解できた。畠山さんの主張、生きざまは他のこと全てに通じる。諸外国では40年前にすでに先住民の人権を認めているのに、また国連から指摘されているのに政府が全く姿勢を変えないことに驚かされた。このことは他の人権問題に対しても同じだ。この映画をたくさんの方に観てもらいたい。
法律があるから守るのではなく、法律そのものの是非を問うことから考えなければならないことがよく分かりました。サケ漁の問題だけでなく、アイヌの居住地や給与地、遺骨返還などの問題も取り上げ、それらに関係者
の発言を加え、先住権の問題が理解できました。
多くの方々のご意見をうかがうことができ、大変勉強になりました。特に、藤野監督の「(畠山さんがサケ漁の許可申請を出さないのは、それをすると)アイヌにサケ漁の権利がなく、道知事に権利があることを認めてしまうからだと思う」のご発言にはっとさせられました。
『ゴールデンカムイ』などのサブカルのなかで提示される、和人に都合のよい、可愛らしく聞き分けのよいアイヌ像。それを「リアル」だと「理解」し、「消費」することで、「アイヌを保護してあげている」つもりになってしまう「私たち」。そういう「理解(支配)可能なアイヌ」を求める私たちに対して、「おまえたちがどう思おうが、これがアイヌだ」と突きつけるような力強い作品だと思いました。
作品途中大通り公園で畠山さんが、アイヌの先住権を必死に伝えてる場面で、通行人がスルーしてしまっている光景を目の当たりにして、マイノリティであるアイヌは自ら行動にでなければならないのに対してマジョリティの通行人は気にする必要がないのであろうと感じ、見える化することがどんな意味を持つのか理解が深まりました。
「日本人」だという帰属意識はあったものの、自分が「和人」であるという自覚はありませんでした。そのことから、自覚がすべてなのではなく、他者からどう見られているか、それがどのような理由から生じている意識なのか、それをひっくるめて「自分が帰属していると信じるグループの中の「自分」であるということを感じました。うーん、でもそれは差別されている側に同じように当てはめてしまうと問題がありますね…。
また、宇佐さんの演奏に「トンコリの生演奏を初めて聴けました。素晴しかったです」「宇佐さんのライブがすてきでした!」「演奏が素晴らしかった。感動しました」との感想が多数寄せられました。
ご参加、ご協力くださったみなさま、ありがとうございました。
※本稿は、さっぽろ自由学校「遊」の会報誌『ゆうひろば』第193号(2024年12月)掲載の原稿を再編集して公開しました。