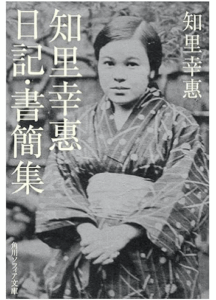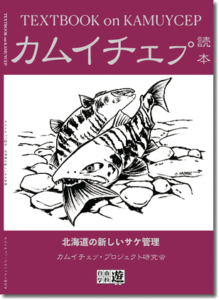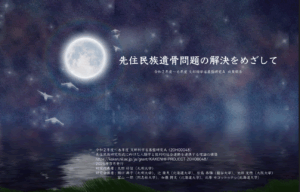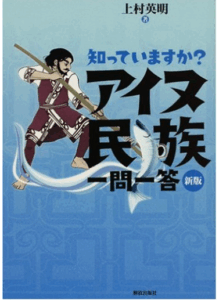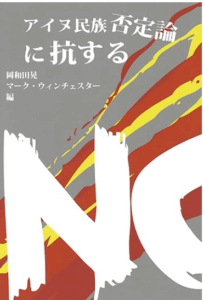・『写真が語るアイヌの近代 「見せる」「見られる」のはざま』
大坂拓 著 2025年 新泉社 ジャンル 史料分析
マコトを写すと書いて「写真」。だれでも画像補正アプリを使う現代では名称ごとフェイクとすら言えそうですが、本書の著者は、そんな写真のさらに内奥に潜む「真実」を、見事な手際で引き出します。
吟味されるのは、19世紀末から20世紀にかけて、北海道島南部の噴火湾(内浦湾)沿岸部などで撮影され、書籍挿画や絵ハガキとして流通した多数の「アイヌ風俗写真」です。被写体は必ず先住民(アイヌ)、撮影者と購読者はもっぱら植民側(和人)――というアンバランスを提示するだけにとどまりません。膨大な周辺史料から直接/間接の証拠を積み上げて、撮影者・被撮影者・撮影日・撮影地・撮影状況を突き止めるようすは、まるでミステリを読んでいるよう。
写真がその名に反してきわめて人為的な「作品」である点は、当時も今も変わりません。
たとえば、「アイヌ室内の光景」と説明文をつけて、さも日常生活を写したかのような絵ハガキ(1909年)が、実はセット内で先住民たちに演技させたもの——ヤラセ——だと、著者は見抜きます(p74-90)。
なぜそんな作為が必要だったのか? 著者はそれを〈和人側の基準による換骨奪胎〉と喝破していますが(p171)、残念ながら現在のマジョリティ=入植者社会にも、それはなお色濃いと言えそうです。
著者は1983年北海道生まれ、北海道博物館アイヌ民族文化研究センターの現役学芸員です。本書でたどり着いた地点から、自身はどんな表現を目指すのか。著者の今後の展示や発信から目が離せません。(平田剛士 森・川・海のアイヌ先住権研究プロジェクト副代表)
もくじ