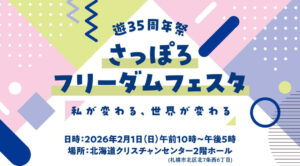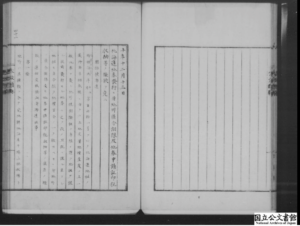平田剛士
フリーランス記者、森・川・海のアイヌ先住権研究プロジェクト副代表
「松浦武四郎は北海道植民者の先駆けのような存在だと思います。先住民族アイヌの諸権利を『見える化』するのに、そのような人物の著作を利用するのはなぜですか?」
過日、さっぽろ自由学校「遊」の講座にお招きいただいて「『北海道の開拓/開発』と先住権」の題名でスピーチしました(2025年1月20日)。終盤、質疑応答の時間に一人の受講者さんからちょうだいしたこの質問に、私はうまくお答えできませんでした。
講座はこんなふうでした。
先住民族の諸権利を〈「当たり前の権利や自由」のうち、国家の法律による規制はもとより、非先住民のマジョリティの価値観の押しつけ、一方的に従わされている法律、植民地開発にともなう環境破壊などによって、先住民族がいま制限されているすべて〉と定義づけてよいのでは?――とお話ししたうえで、後段の「開発にともなう環境破壊などによって、先住民族がいま制限されている」具体例を、ヤウンモシㇼ=北海道島で最大の流域面積を誇る石狩川を例にお示ししたのですが、地元の先住民たちが諸権利・自由を制限される前と後(現在)の環境変化を確かめるのに、古い記録を利用しました。松浦武四郎著『石狩日誌』(1860年刊行)という書物です。日本政府が、それまで蝦夷地などと呼んでいたこの島に「北海道」と命名して植民地化を宣言したのが1869年(明治2年)。その直前の石狩川かいわいの様子をうかがうのに、探検家・松浦武四郎が残した遡行記録(巧みなイラストつき)はうってつけのテキストです。講座でも、武四郎のリアルな描写に賛辞を送りつつ「多少の脚色はあるかもしれないが、おおむね信頼できるデータ」と紹介しました。
その松浦武四郎(伊勢=現在の三重県松阪市生まれ、1818年-1888年)に「北海道植民者の先駆け」の顔があることは間違いありません。彼が『石狩日誌』に記録した1857年の石狩川遡行は、箱館奉行所(江戸幕府の出先機関)の指令を受けて「お雇い」の肩書きで出発したものでしたし、「蝦夷地のスペシャリスト」と見なした松浦を、王政復古(いわゆる明治維新)後の新政府は、1869年8月11日に設置した開拓使の大主典(今でいう次官クラス)に抜擢しています。新政府はすでに蝦夷地=北海道を植民地化すると表明していましたから(「蝦夷地之儀」1869年6月30日)、以来そうされ続けてきた側(先住民族)に「アイヌモシㇼに侵略の触手を伸ばす和人政府の手先」と指さされても、松浦は言い訳しなかったでしょう。
『石狩日誌』の序文に、松浦は〈石狩川上流から各地への道筋を検討するよう、箱館奉行所からの命をうけてこの方面を探査した〉(松浦武四郎著・丸山道子訳『石狩日誌』1973年、凍土社刊、p16)と記しています。時代背景を考えると、ロシアとの国境争いに備えた活動の一環といえます。そうした植民地主義色の濃厚な目的と方法で集められた情報を、180年後の私たちが単に「当時の風景や人々の様子をうかがい知るのにうってつけだから」と便利に利用してしまうことに、きっと冒頭の質問をくださった方は、違和感を抱かれたのだと思います。
スピーチを聞いてくださった方のそんな違和感をその場で拭いきれなかった私は、歴史資料を引用する場合の注意深さを明らかに欠いていました。せめて上に書いたような解説を尽くして、それでもなおこのテキストをアイヌ先住権を論じる際の材料にする必要性を、きちんと説明すべきでした。
講座から3日後、かねて予定していた「森・川・海のアイヌ先住権研究プロジェクト文献調査チーム」のオンラインゼミ(非公開)で、参加くださったみなさんと、このことについて意見を交わしました。それぞれ自分の調査や執筆経験を振り返りつつ、歴史資料を取り扱うさいに留意すべきポイントを確認しました(このエッセイは、それを踏まえて書かれています)。
- あらゆる過去作品について、それを書いた個人や組織の意図や立場性(ポジショナリティ)、時代背景を確認すること。
- 「どんな著者も、偏りを生じさせるもの(バイアス)から逃れられない」と意識すること。
- 「とりわけ無文字社会に対する植民地化の局面では、地域情報の一方的なテキスト化や地図化それ自体が権力性・暴力性をはらんでいる」と意識すること。
- その上でなお、その資料を利用する理由をきちんと説明すること。
「森・川・海のアイヌ先住権を見える化する」と銘打つこのプロジェクトで、少なくとも日本政府による「北海道改称」(1869年)以降156年にわたる諸権利侵害を調べあげるのに、記録文献は欠かせない材料です。そのひとつひとつを丁寧に読み解いていかなければ、と肝に銘じます。