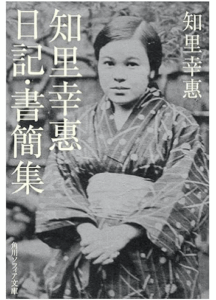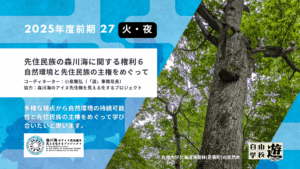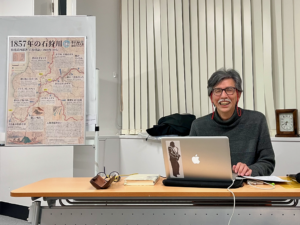自由学校遊 24年後期講座:先住民族の森川海に関する権利 5—アイヌ先住権を“見える化”する
3月17日(月) 第6回
座談会 先住権の回復に向けて part 2
●藤原 顕達(ふじわら けんたつ)
千歳生まれで恵庭育ちです。今は60 歳です! 各地方のアイヌ民族の事が知りたくて顔を出しています。
●小笠原 小夜(おがさわら さよ)
森川海のアイヌ先住権を見える化するプロジェクトメンバー。自身のルーツであるアイヌをテーマにイラストを描いている。
●井上 千晴(いのうえ ちはる)
浦河町出身・森川海のアイヌ先住権を見える化するプロジェクト副代表・一般社団法人アイヌ力( ぢから) 事務局
●沖津 翼(おきつ つばさ)
北海道帯広市生まれ、首都圏でのアイヌ活動後、現在は札幌市在住、道内のアイヌの仲間と共にアイヌ儀式などに加わり活動中。 アイヌ議会共同代表 、アオテアロア・アイヌモシリ交流プログラム実行委員。
●木村 二三夫(きむらふみお)
アイヌ ネノ アン アイヌ「人である人」実行委員会共同代表
●清水 裕二(しみずゆうじ)
北海道中札内高等養護学校元校長・江別市第二町内会元会長・日本社会教育学会元理事、会員
●進行:川上 恵(かわかみ めぐみ)
森川海のアイヌ先住権を見える化するプロジェクト運営委員
(肩書は講座開催時のものです)
はじめに ―森川海 事務局 小泉より―
今日の座談会を始める前に、前回の座談会の際に確認が不十分だったこと、アイヌの方々にご負担をかけてしまいましたこと、まずは主催者としてお詫び申し上げたいと思います。
経緯としては、前回の座談会の最後に、参加者から登壇者に心理的負担をかけるような発言がありました。その対処が運営側として十分でなかったため、皆さまに話し合いのお時間をいただき、ご意見を頂戴しました。
第2回の座談会を始める前に、改めて本講座の目的を、参加されている皆さんと共有したいと思います。本講座は、アイヌ民族自身が先住権について、どのように考えているか対話をし合うことが目的です。アイヌ民族の中でも権利について発言することは、ハードルが高いことです。先住権について発言することは今日の日本の状況の中で、嫌がらせを受けたりすることもあります。それでもこの講座ではあえて「場」を作っています。そのため前提として、参加者のみなさんには、登壇者の皆さんのお話をきちんと受け止め、登壇者が安心して話せるような場作りに協力してほしいです。ですので、参加者の皆さんに特に発言は求めませんこと、あらかじめご認識ください。
前回の座談会を振り返って
いま、思っていること
 川上
川上前回の座談会のアンケート結果を元に、話を進めたいと思います。
まず、アンケートにとてもたくさんの意見があって嬉しかったです。
多くの方々が気づき、自覚が必要、アイヌの方の考えが聞けて興味深かった、なんとかしたい、と書いてくれて「やってよかった」と感じました。
また中には、なぜ奪われた側のアイヌが主張しなければいけないのか、先住権の問題をアイヌだけに押し付けているのでは、など熱烈なメッセージもありました。



次のステップは、一緒に行動に移すこと、一緒に問題に向き合っていくことかと思いますが、皆さん、前回の座談会を振り返って思うことはありますか?
「人権や権利に踏み込むと大変だよ」と、とある尊敬するフチが言っていたのですが、これまではその「大変」がどんなことなのか、あまり実感がありませんでした。でも、前回の座談会で「こういうことなのか」とわかりました。自分の芯をしっかり持って「逃げちゃダメだ」「わたしたちの世代でやらなくては」と思いました。
そして、アンケートを読んで「アイヌだけじゃない、和人もやるべきだ」という和人の方々の意見も拝見できて力になりました。少し怖さがあるのも事実ですが、このような座談会を次につなげていきたいです。
権利問題は難しい印象で、身近ではないと思っていて避けがちでした。
でも、最近周りに権利について考えるアイヌが増えてきたり、アイヌ自身が学ぶ場面・姿勢が目に見えて増えてきていると感じます。私自身も様々な場面で権利に関して勉強する機会が増えてきました。
前回の座談会で八重樫さんに「身近なことから考えよう」と言ってもらったことで気が楽になりました。私はいつも、アイヌ語の言語習得に苦しんでいて、アイヌ語を自然に身に着けながら成長したかった、という思いがあるのですが、こういった(アイヌ語の)権利復興をもっと広げていきたいと思っています。
こういう話し合いは大事ですよね。もっとアイヌ同士の話し合いが増えていかなくては、とずっと思っています。前回、若い世代のアイヌが来て発言してくれて、よかったと思いました。あちこちで若い世代の人たちが出てきているので、こういう場に足を運んで、聞いて、発言することにつながっていってほしいと思っています。
認識、発信、連帯、行動



アンケートに、「今後アイヌにとって最も大切なことはアイヌ内の連携」というような記載がありました。私は個人的には、和人も含めて全体で連帯していかなければいけないのでは?と思います。
同じくアンケートにあった「国が、国がという(アイヌの)発言が後退的で、権利は誰かに認めてもらうものではなく、アイヌ自ら発信、主張しなければ」という発言も、少し違うのでは、と感じてしまいます。
アイヌ民族は、今も昔も自ら発言しています。「国が国が」と言わなければいけないのは、国が動いてくれないと世間は動かないからです。その結果、今も差別がなくなっていません。自分たちだけでやっても限界があると思います。その背景を省みないこの発言が悔しかったのですが、皆さんのご意見も聞けると嬉しいです。
私も、何十年と行動を起こしても、現状は何も変わらないことを痛感した経験があります。親世代のアイヌの方たちが、アイヌ民族の正しい情報、正しい歴史を教科書に載せてほしいと何十年も主張してきました。
でも現状は、副読本1があるのに使われていなかったり、道外に至っては副読本の存在すら認知されていません。
一般の教科書にもアイヌ民族の記載は限られていて、アイヌ民族を取り巻く状況は、様々な声や運動にも関わらず、変わっていないのは事実だと私も実感しています。
アイヌ民族だけではなく、和人も含め国全体、みんな自分事のように取り組んでいかなければいけないと思います。同時に、同胞がまとまっていないという現状もあります。道のりは長いと思うけど、いろんな世代が集まって一緒にやっていこうとすることが大事だと感じています。
このコメントは、「もっとアイヌ自身が頑張れよ」ってことだと思います。ここにいる人は分かっている人が大半だと思いますが、「頑張ってるわ」って話です。
まだ知らない人に言うと、私たちはアイヌのこと(例えば踊りや歌など)で生きている訳ではないです。仕事をしながら、喪失の危機を乗り越えて先祖から受け継いだアイヌということを、もっと深めるように学んでいるし、一人ひとりの努力で絶やさないように(文化活動含め)しています。
前提として、アイヌ民族が否定されてきたという歴史がどれだけ続いてきたのか、アイヌ自身も知らないし、知りたくない歴史、子どもに知ってほしくないと感じることもいっぱいあります。自分がアイヌになった時も、目にも耳にも入れたくない、考えたくないような歴史を知ることに、まずは覚悟を決めました。それを知ったから、趣味や遊びでアイヌのことをやっている訳ではないです。
先祖から受け継がれた歴史の先に、自分たちがいるんです。当たり障りのない内容だけで…という話が出てくるのはわからなくもないですが、アイヌ当事者はそうではいけないと感じています。アイヌ当事者は嫌でも知らなければいけない、共有しなければいけないことがあると思っています。
国に求めていくことに関して、一人ひとりが頑張っても前に進まない、という前提があるから、どうしても国に働きかけなければいけません。そして国に求めていくことは何十年も続けています。でも国は動いてくれません。だからこそ、アイヌ自身が意識を共有する、連帯することが必要ではないでしょうか。共有・連帯することでまとまった大きな集団(クラスター)となれるのではないでしょうか。
今、遺骨問題に取り組まれたり、先住権に関する裁判などをしているアイヌたちもいますが、こういった動きが全体で共有しきれていないと感じます。アイヌ自身で話し合いなどをして議論を深めていくことが、自分たち自身の力を取り戻すことになるかと感じます。
10年位前に海外の先住民族と交流したのですが、大きな学びの一つが、自分たちの力を取り戻すことでした。力を取り戻して、仲間を作っていくことの大切さ。それは国と闘うための武器にもなります。アイヌ民族の運動も見て来ましたが、まだばらばらで、みんなそれぞれ頑張っていても点と点でつながっていないんですよね。それぞれの立場、ポリシーなど色々あると思います。
でも、社会的弱者として立たされてきた歴史の中で、一つの権利を取り戻すために協力していく、連帯していく、そして共有することの必要性を私は訴えています。なので「当事者がもっとやれ」と言うだけではなくて、私たちが述べたことを汲んで、どう助け合えるのかにフォーカスしてほしいです。それが連帯ではないでしょうか。
遺骨返還の話が出ましたが、北大からご遺骨が返還されたときは、謝罪の「しゃ」の字もないくらいでした。その後も、遺骨返還に関して何か決まりがあるらしいですが、それに則ると謝罪する必要はないと言われました。本当に悔しいです。
加えて、1000体くらいのご遺骨がありますが、返還されたのは100体強ほどです。高校生の時に、静内の墓地からご遺骨を掘り出している和人の姿を見たことがあります。その中から約200体が東大に行っていると思います。今はその多くを象徴空間に集めていますよね。私は怖くてあそこには入れません。ご遺骨になっても囚人のような扱いをされて、先人達のことを思うと悔しくてなりません。
私も遺骨問題について、先人たちが侮辱されているということは、今を生きる私たちが侮辱されているのと同じことだと思っています。これは絶対に許せません。盗掘されたご遺骨はあるべき姿に戻し、謝罪をさせる、この思いで何年も遺骨問題に取り組んできました。
世界のいかなる国家、民族にも聖域があります。何人もこれを犯してはならないと思います。アイヌ民族は屈辱的で困難な歴史を歩まされてきました。アイヌたちの霊が眠る、祖先のお墓を心無い研究者が破壊したことは、霊魂に対しての冒涜、人権侵害、そして人道上決して許されることではありません。自分の身に置き換えて考えてみてください。これを忘れないことが大切だと思っています。
連帯に関しては、みんな良い意見を持っているのだから、ワンマンショーではなくて、みんなで歩調を合わせることが大切かなと思っています。


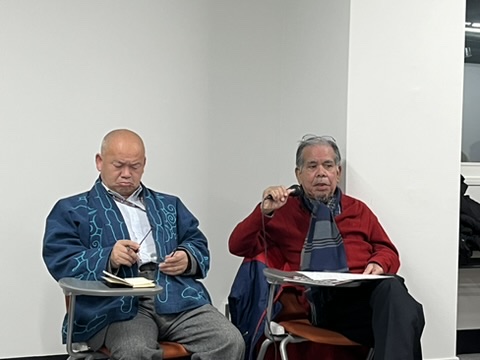
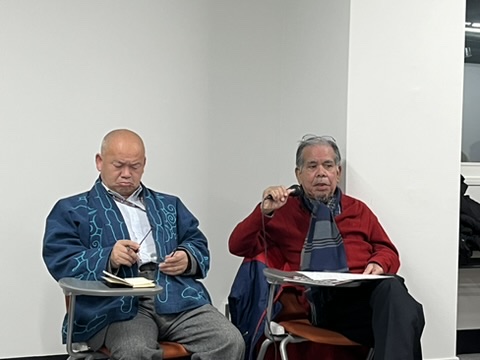
教育と副読本に関して



副読本の話が出ましたが、実は副読本に思うところがあります。
小学生用はわかりやすく作られていて、個々のアイヌが違うことを伝えるのはあまり良くないかと思い、私自身も活用することがあります。
札幌のアイヌ文化交流センターで小学校4年生と中学校2年生を対象に行われる体験プログラムや、各学校でこの副読本が配られていますが、活用していない人がほとんどなのが事実です。活用している人もいると思いますが、副読本という教材があるのにも関わらず(ほとんどの学校で)使われていないことが多いんです。



もう一つ問題だと感じるのが、アイヌ民族に関する授業をするのは良いと思います。でも、すごく悲しいことにテストには出ないんですよね。以前学校で講演した時も、担当の先生に「この講演内容は、テストに出ない」と、話す前に言われてしまったんです。テストに出ないことは、児童生徒の多くは真剣には聞かないですよね。でも、自分たちが生きて立っているこの地を知る、というのは、とても大切な授業です。皆さんどう思われますか。
副読本のことは、私も何も知らなかったし、自分で読んでもさっぱりわからなかったというのが事実です。先日、副読本の改定会議に参加して、一応令和8年度に改定されるというになりましたが、内容に関してアイヌ協会が口出しできるのか、どんなものが出来るのか、想像がつきません。一応、北大アイヌ・先住民族研究センターなどの研究者と相談しながら作るようですが…
先ほど話にありましたが、口には出せないようなひどいアイヌ民族の扱いがあったのは事実です。文章には詳細まで残っていないかもしれませんが、だからこそ後世に伝えていく必要性があると感じています。
ここまで皆さんのお話を聞いていて、素晴らしいお考えをお持ちだなと感じています。アイヌ文化も大事だと思いますが、その前に自らの権利を主張できる日常生活にしましょうよ、と私もずっと言ってきました。
ある時に、北海道大学開示文書研究会共同代表の殿平善彦さんは、「アイヌの皆さんの発言を聞いて、和人がもっと謙虚にアイヌの存在を理解しなければおかしい」と言われました。つまり、北海道にいるシサムの皆さんはアイヌに対して「上から目線」という感覚が今現在もある、それを誰も否定できないということです。いじめられたアイヌからすれば、この発言に非常に感銘を受けました。
共生社会を作ろうというのであれば、アイヌ民族も社会になじむように一生懸命やりますし、同時にシャモもこのような感覚を持たなければいけないと思います。そうすれば、共生はもっと早くできるのではないでしょうか。
副読本の改定も、副読本作成の編集委員に断りなく改訂しようという問題がありました。それに抗議したら「ちょっと文字を変えるくらいです」と言われました。それでも、一言あってもいいのではないでしょうか。
アイヌ民族の歴史150年くらいを見てみても、悲惨な歴史をずっと負わされてきました。それに対して、シャモが上から目線でなく、謙虚に反省する姿勢が必要ではないかと思っています。アイヌ民族が発言しやすい「日常」になることが、今、必要だと思っています。共生というのであれば、シャモももっとアイヌのことを知ろうとする姿勢が必要です。



会場でも拍手が沸いています!
私は副読本をもっと活用すべきだと思いますし、テスト内容にアイヌ民族のことを入れるべきだと考えています。皆さんのご意見はいかがですか?
先ほどと重複しますが、以前から思っているのは、副読本は道内の小・中学校だけへの配布ではなく、まず全国に配布してほしいなということです。
副読本は毎年財団から送られてきますが、毎年同じような内容ですよね。模範解答っぽい内容というか…
そういえば、先日、入試か何かの社会科の答えに「アイヌ」という答えがあったとテレビで見ました。とにかく多くの方に関心を持っていただきたいです。
副読本については全然わからないので、話がそれて、先ほどの話と重複しますが、アイヌ民族には何億年も前の先人から受け継いできた歴史があります。その祖先のお墓を、身内の許可もなく盗掘するということは、非常に侮辱的で非人間的な行為だと思っています。なのに、今も研究にご遺骨が使われようとしています。盗掘というのは、人として絶対にあってはならない恥ずべき行為だと思います。許せません。
あってはならない、と言うと、杉田水脈のアイヌ民族や在日コリアンに対する発言も、です。それなのに、参院選の候補者となるというニュース。これってどうなんでしょうね。
まさに今、そんな議員候補がいるということが、問題だと思います。
副読本に関連して学校教育面で言うと、子ども時代から学ぶ機会があると違うのではないかと、個人的には思っています。
私の地域では、アイヌ文化やアイヌがやっていることを子どもが学ぶ機会が多くて、ムックリの発表会をするとか、テストに出るか出ないかではなく、みんなで取り組んでいます。テストに出るから勉強するとかではなく、同じ地域にアイヌ民族が住んでいるんだよ、というような導入など、先生の意識が変わらないと何も変わらないので、それが悔しいです。私の住んでいる地域や北海道だけでなく、日本全国の学校でアイヌ民族の勉強の機会をもっと増やしてほしいです。
今度、あるフチのエッセイが中学校の道徳の教科書に載ります。全ての中学校で取り入れるわけではないですが、これも第一歩になるのかなと思っています。
私は副読本を使う立場にはないので、あまり目にすることもないのですが、小学校の教科書か副読本的な物なのか、娘の教材を見ました。大体の内容はまあいいのかなと思ったのですが、一部「ちょっと待ってくれ」と思った部分がありました。
アイヌ民族は「昔の人」のようなステレオタイプの文脈で書かれていたんです。それこそ、昔いた人々、と思い込んでしまう可能性がある表現です。思わず娘に、「先生に、これは違うと言っておけ」と言ってしまいました。この表現は結局、今の時代になっても何も変わっていないことを表しているのではないでしょうか。
副読本を改訂するならもっと本腰を入れて、遺骨問題のこと、サケの漁業権のことなど、今起きているホットでリアルなことを書いて欲しいです。国が今までアイヌ民族から奪ってきたこと、アイヌ民族に対して何の救済もしていないことが今も続いている、という事実を学校で教えてテストの問題に出せばいいと思います。
みんなと議論したいこと



皆さん、様々な思いや意見を共有してくださりありがとうございます。
ここまでで、何か補足や追加でコメントされたい方はいらっしゃいますか?
海外の先住民族を訪れて思ったことですが、先住権を回復するために、先住民族サイドからどう国(政府)に発信していくかがすごく勉強になりました。いきなり大勢を相手にするのではなく、ピンポイントで議員を訪れて、何度も何度も話をしたり、勉強会を開こうとされていたんですよね。
そうすると、国会議員も人間なので、何かに一生懸命になっている人の話は聞くようになっていくんだそうです。そしてそういう人を取り組んでいくと教えてくれました。それを見て、先住民族自身が自分たちの状況を少しでも良くするために動くことが大切、待っていてはダメな部分もあると感じました。先ほどの通り、アイヌ民族も行動は起こしていますけどね。
待っていても国は動いてくれないので、当事者が連帯して、考えて提案していくことも必要ではないかなと感じます。例えば副読本に関してであれば、こんな副読本では不十分だよね、こんな学習方法では不十分だよね、では、こういうアプローチはどうだろう?公教育の道徳の時間を、こういう風に使えないだろうか?というように、アイヌ自身が提案していく。みんなで会議をしてカリキュラムを自分たちで考えてもいいかもしれません。これはアイヌ民族も行動していけば実現出来ると思っています。
アメリカのある先住民族も、最初は彼らの活動にどこからも予算や支援はなかったそうです。でも行動し続けた結果、数年後には、州からの予算が付くようになっていったんです。こういう海外での実践例を見てきて、状況が代わる可能性を見てきたので、アイヌ民族の中でも実現していきたいと思っています。
マジョリティが変わるのはもちろん大前提です。でも同時に当事者が先住民族自身のルールを持っていっていいんだ、という意識を持つことも必要ではないでしょうか。色々時間がかかるかもしれません。でも、絶対できると信じています。



私も共感します。でも連帯って大変ですよね…
そこが大変なのはもちろんです。
でも、私たちが今行っている座談会も5年前にはなかったですよね。5年前には想像できなかったことでも今は出来ているし、前回は若い世代のアイヌも来ていました。これからも若い人たちがきてくれると思います。なので、国や例えば学校などがやらなければいけないように、アイヌ民族が連帯して道を作ることも必要だと思っています。
実は、とあるアイヌ民族の方と、アイヌ同士の連帯の話を先日したんです。私は、こういう話が出来るアイヌの仲間がいつか絶対できると信じてここまできて、実際会えたんです。これはすごく嬉しかったです。
人の前に立つのは勇気が必要で消耗します。でも、フチやエカシが今までやってきてくれました。それを引き継いで、そういう仲間たちとつながってもっと続けていく、もっと副読本、教育に対しても声を上げていくことをやっていきたいと今は思っています。


海外の会議への参加や具体例をみて



考えを共有してくれてありがとうございます。
連帯するって本当に難しいですね。私も、海外の事例を見聞きすると、アイヌ民族が遅れている部分は否めないと感じています。
以前、ハワイの先住民族の会議(世界先住民族教育会議2)に参加したときも、海外の先住民族の状況に、憧れも感じました。
ハワイで行われた世界先住民族教育会議(ウイプシー / WiPCE)に参加しました。ハワイには、幼稚園のようなところで、ハワイ語しか話していけないという環境があるんですよね。遊具などにもハワイの知恵がちりばめられていて、その場にいるだけで子どもたちが言語や文化などを知れる空間になっているんです。アイヌ民族でも、同じような空間を作る話が持ち上がった覚えがありますが、まだ実現には至っていません。
あと衝撃を受けたのが、現代的な生活(スマホやPCの利用など)や人の出入りが制限されている島があり、そこでは伝統的なハワイアンの生活を伝承する空間が出来ているんです。アイヌ民族にもそういう島が一つ欲しいですよね。
今は海外の実例を見て、「うらやましいな」と感じるところでまだ止まってしまっている気がしています。
私、「Hawaii」というのもハワイ語だと知りませんでした。
でも、海外はやり方がすごいな、早いなといつも思っていて、例えばハワイは、ハワイ語や伝統を復活させる、となったらすぐに大学に学部を設立したりされるんですよね。
先日、台湾から来られた先住民族の方や大学教授とお話ししたのですが、台湾では16部族すべてに議席があるんですね。一部族に一議席と憲法に書かれていると聞いて驚きました。
海外では、例えばフィンランドのサーミの方たちは博物館の館長なども、自分たちで務められていますよね。


まとめとメッセージ
海外の事例は確かにすごいです。でも、一言だけ。
アイヌ民族は恥ずべき人種ではありません。堂々と生きましょう。多くの仲間を増やして、今日この座談会に参加されている若い方たちに、がんばってもらいたいなと思っています。後方からサポートしていきますので。
カント オロワ ヤク サク ノ アランケプ シネプ カ イサム
これは私が好きなアイヌ語です。天から役目なしに降ろされてきたものは何一つない。という意味です。地球上に降ろされたからには、皆さん一人一人にも大きな役目があるということです。
聞く耳を持って謙虚であることが大切だなと、今日の話から思いました。
今日も含めて、私がいつも話していることは本音です。こういう座談会をぜひまたやっていきましょう。
どんな反応が返ってきてもいいので言いますね。最近、アイヌ民族の周りにいるアイヌではない人たち(活動をサポートする人など)の立場性-ポジショナリティ が問題になっているのは、事実だと感じています。アイヌ民族がもっと連帯性を帯びてきたときにも、アイヌ民族に関わろうとしてくれるのであれば、それぞれの垣根を越えて関わる、という気持ちや姿勢を持っていてほしいと思います。
アイヌだけがわかっている、シャモだけがわかっている、という状況ではなくて、みんなで。それが大事だと思います。



今日の座談会でも、皆さんそれぞれの熱い思いを聞けて良い時間になりました。前回と今日で、色々思ったり感じたりされたと思いますが、それを今後発信、行動に繋げて、一緒に、共に問題に向き合っていけたらと感じました。
先ほど、好きなアイヌ語を紹介してくださった方がいましたが、もう一つ、良いアイヌ語があります。
ヌヤン ヌカラヤン ピラサレヤン
聞いて、見て、広げていってほしいので、同じ思いで発信出来たらいいなと思っています。皆さん、ありがとうございました。
座談会全体を振り返って
今回の講座は、前回の内容を振り返る形で始まりましたが、そのことが、大きな課題である「マジョリティとしての立場性」への参加者の方々の批判的思考を促す契機となりました。特に和人の参加者からは、このテーマについて深く考えるきっかけになった、との声が多く寄せられています。
上のまとめのとおり、登壇者が、前回の参加者の反応を受けて問いを投げかけるスタイルを取ったことで、和人としての加害性に対する自覚が喚起されたようでした。特に大きな反響があったのは、前回のアンケートで(おそらく和人である)参加者から寄せられた「アイヌ同士の連携の重要性」を強調する声や、「国への働きかけ方」に対する疑問に対して、進行役の川上さんや登壇者の方々が返した応答でした。「アイヌだけでは問題は解決しない」という登壇者の言葉を受けて、参加者からは、
・「和人としてどのような努力が求められるのか」、
・「自分も有権者の一人として、国を動かすためにどうあるべきかを深く問われた」
との声が寄せられました。
また、琉球の先住民族運動に詳しい参加者からは、「琉球においてもヤマトンチュ(和人)が越境しようとする傾向が見られる」との指摘があり、他の先住民族運動と比較しながら考える視点も挙げられました。さらに、副読本をめぐる議論からは、現行の教育制度に内在する課題が浮き彫りとなり、社会全体を対象とした教育の重要性を実感したとの声も複数寄せられています。
「今回の講座では、より多くの“本音“を聞くことができた」との感想も多く見られ、登壇者の言葉が参加者に真摯に受け止められたことがうかがえます。
2024年度後期の講座全体を通しては、専門家による人権や先住権に関する基礎的なレクチャーをはじめ、国連や海外におけるアイヌ民族の活動紹介、聞き取りを行ったアイヌ・和人双方のメンバーによる内省、歴史資料との向き合い方、そして前回、今回の座談会における先住権をめぐるディスカッションなど、さまざまな視点から森川海のアイヌ民族の先住権を考えてきました。
今回の講座は、これら一連の学びを振り返る集大成の場となったと言えるでしょう。2025年5月から始まる来期の講座も、みなさまと共にさらに考え、行動するための糧となることを願っています。
(まとめ:双木麻琴、七座有香)
- 副読本
主に小中学校においてアイヌ民族に関する学びを深める教材が発行され、道内全ての小中学校に配布されている。しかし、副教材という性質上使用は必須ではなく各教師に任せられており、学校や担当教員によってばらつきがある。https://www.ff-ainu.or.jp/web/potal_bunka/details/post.html ↩︎ - 世界先住民族教育会議 ※国連該当ページ一部抜粋、まとめ担当和訳
世界先住民族教育会議(WIPCE:World Indigenous Peoples’ Conference on Education)は、1987年にカナダ・バンクーバーで始まった。初めてのWIPCE会議では、長老や地域の(先住民族の)知恵を持つ人たちが「コミュニティ」の大切さを示し、それらが会議の目的や意味に深く関わっていることが強調された。WIPCEは現在、先住民族の文化を大切にし、心を豊かにする教育をつくり広めようとする個人や団体の運動となっている。https://wipce2025.com/about/ ↩︎